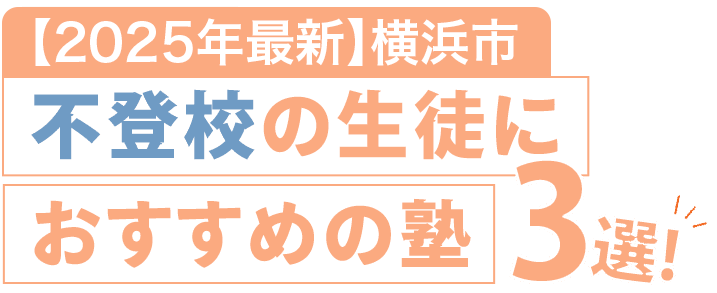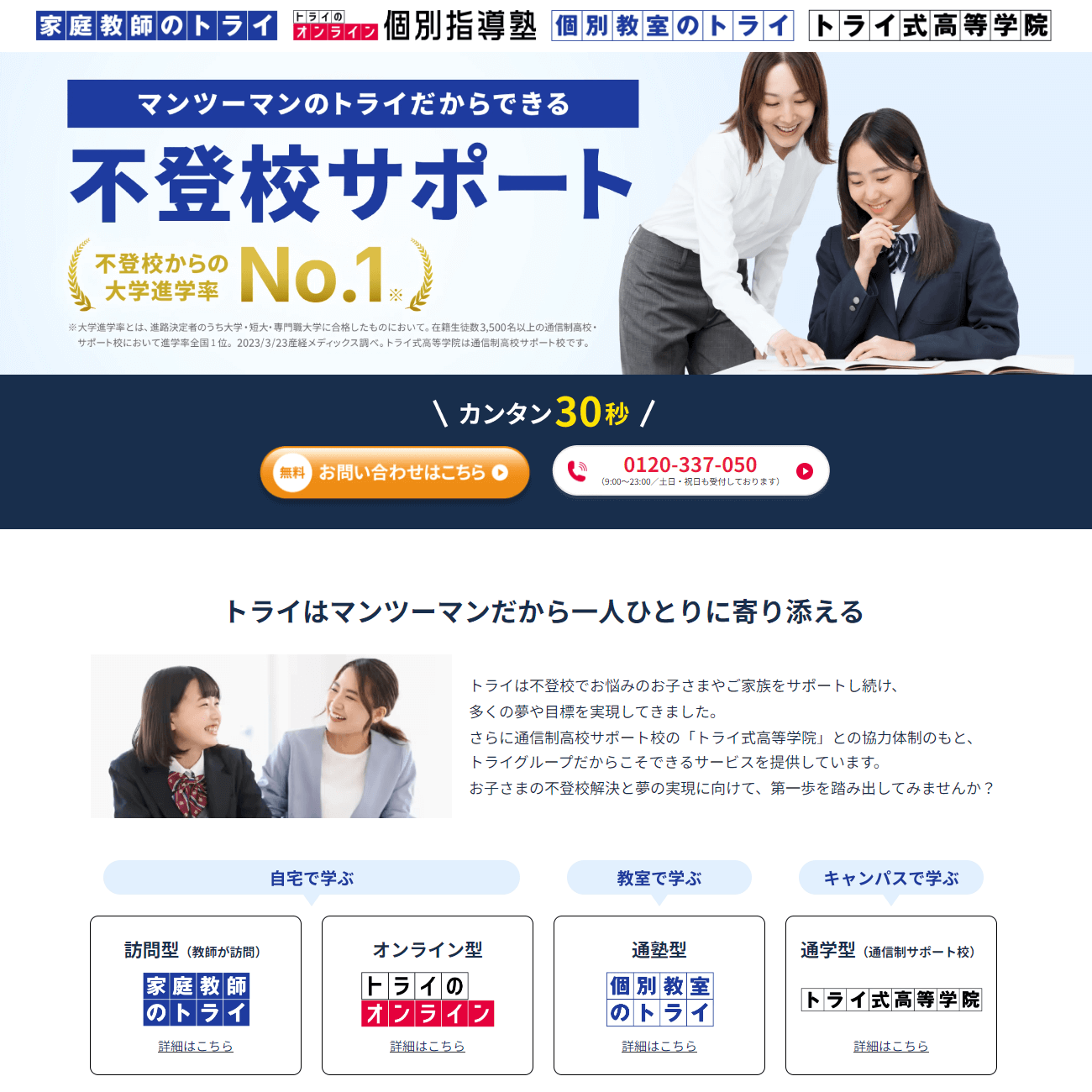不登校は「怠けている」「甘えている」などと考えられることが多いですが、そうとも言い切れません。子どもの性格だけでなく、学校での人間関係や学業のプレッシャーなど、さまざまな要因が絡み合って起こるものです。深刻な悩みやストレスの末に登校できなくなるケースは少なくありません。本記事では、不登校になる主な理由を3つに分けて解説します。
不登校とは?基本的な定義を解説
文部科学省の定義によると、不登校とは「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的な要因・背景により、年間30日以上登校しない状態」を指します。病気や経済的理由による欠席とは異なり、学校に行きたくても行けない、もしくは行くことに強い抵抗感を抱えているケースがほとんどです。
文部科学省が令和5年度に実施した調査結果では、小中学校の不登校児童数は過去最多の34万人超えとなっています。また、高校における不登校の生徒数は約6万8,000人にものぼり、3年連続で増加しています。
不登校は、誰にでも起こり得る問題であり、今後も増加傾向にあると想定されています。単なる「怠け」ではなく、子どもが抱える深刻なストレスや不安のサインである可能性が高いため、家庭や学校、社会全体で支援する必要があります。
不登校になる要因は複雑に絡み合っている
不登校の背景には、さまざまな要因が考えられます。一つの要因ではなく、複数の要因が絡み合っていることがほとんどです。ある日突然学校に行けなくなったように見えても、実は長期間にわたる小さなストレスの蓄積が引き金となっているケースも多くあります。
子ども自身の性格や体質、家庭内の雰囲気、学校環境や友人関係、学業に対するプレッシャーなど、さまざまな要素が影響して不登校を引き起こします。そのため、不登校を「なぜ行けないのか」と一方的に責めるのではなく「どうして行けなくなってしまったのか」と寄り添いながら、背景を理解していく姿勢が大切です。
不登校になる3つの主な要因
不登校のきっかけとして挙げられることの多い3つの要因を紹介します。
人間関係のトラブル
不登校のきっかけとして最も多く挙げられるのが、人間関係の問題です。クラス内でのいじめや無視、友達とのトラブル、教師との不和など、学校内の人間関係がストレスとなって登校を避けるようになる子どもは少なくありません。
また、直接的ないじめがない場合でも、「友達ができない」「自分の居場所がない」と感じて孤立感を深めてしまうこともあります。学校という閉ざされた空間での人間関係は、子どもにとって非常に大きな意味を持つため、小さなきっかけでも精神的な負担につながることがあります。
不登校の傾向が見られた際には、むやみに心配するのではなく、子どもの話をゆっくりと聞いて寄り添うことが大切です。「合う人がいれば合わない人もいる」「自分が疲れない適度な距離で接しても大丈夫」といったように、子どもが抱える不安を丁寧に取り除いてあげると良いでしょう。
学業への不安やプレッシャー
「勉強についていけない」「テストの点数が悪い」「宿題ができていない」といった学業に対する不安も、不登校の要因の一つです。とくに真面目な性格の子ほど、自分の成績に強いプレッシャーを感じやすく、失敗への恐れから登校を避けるようになる傾向があります。
対策としては、学力のサポートを行うのが有効です。子どもが興味を持っている分野や得意教科を中心に勉強を進めると良いでしょう。「どうしてこんな問題がわからないんだ」などと子どもを責めてしまうと、余計に勉強嫌いを助長させてしまうため、注意しましょう。
進路や受験に対する焦りや、「自分には価値がない」といった自己肯定感の低下も、登校への意欲を削いでしまう原因になります。教師や親の期待に応えようとするあまり、自分を追い詰めてしまうケースもあります。
家庭環境・生活習慣
家庭内のトラブルや過干渉・無関心な育児環境も、不登校の背景として見逃せないポイントです。親子関係がうまく築けていなかったり、家庭内での安心感が得られなかったりする場合、子どもは外の世界に踏み出すエネルギーを失ってしまいます。
また、夜型生活やゲーム依存、食生活の乱れなど生活リズムの崩れも登校しにくくなる一因です。学校に行かないことでますます生活習慣が乱れ、負のサイクルに陥ってしまうこともあります。
こうした問題行動は「理想の子ども像」を押し付けられたことによる反発であるケースがほとんどです。親にとって都合のいい子どもであることや頭の良い子であることを評価するのではなく「健康で元気に過ごせているだけで十分」と伝えることが大切です。
思いやりを見せてくれた時にはしっかりと感謝を伝え、子どもに愛情を示すことも効果的です。
不登校からの回復に向けた支援と対応
不登校の解決とは「学校に戻すこと」だけが正解ではありません。子どもが再び社会とつながりを持てるよう、心の回復と環境の整備を同時に進めていくことが重要です。
子どもの気持ちに寄り添う関わり方
まず大切なのは、子どもの気持ちを否定せず、ありのままを受け止める姿勢です。「甘えているんじゃないか」「学校に行きなさい」といった言葉は、かえって子どもを追い詰めることになります。本人のペースで安心できる環境を整え、日常会話や一緒の時間を通して信頼関係を築いていきましょう。
子どもが自分の気持ちを言葉にできるようになるには時間がかかる場合があります。焦らず、沈黙も受け止める姿勢が回復への第一歩となります。
また、親自身も「子どもが学校に行かないことは自分の責任だ」と思い詰めすぎず、自分を責めないことが大切です。家庭全体の安心感をつくることが、子どもが前向きな一歩を踏み出す土台になります。
学校以外の選択肢(フリースクール・在宅学習など)
近年では、学校に代わる学びの場としてフリースクールや通信制・オンライン学習など、さまざまな選択肢が広がっています。自分のペースで学習を進められる環境があれば、「学ぶ意欲」を再び取り戻すきっかけになることもあります。
また、在宅学習から段階的にフリースクールを経て復学するなど、柔軟な選択ができる体制も整いつつあります。無理に登校を促すのではなく、子ども自身が「安心して学べる場」を見つけることが大切です。
さらに、地域によってはフリースクールと連携した行政のサポートがある場合もあるため、自治体の相談窓口に問い合わせてみると良いでしょう。家庭だけで抱え込まず、地域のリソースを積極的に活用することが、回復への近道になります。
専門機関への相談やカウンセリング
不登校が長期化している場合や、本人の心理的負担が大きいと感じた場合は、専門機関への相談を検討しましょう。教育支援センター(適応指導教室)やスクールカウンセラー、児童相談所など、多様な支援窓口が設けられています。
専門家のカウンセリングによって、子どもが抱えている不安や葛藤を言葉にする手助けになる場合があります。また、保護者自身も悩みを抱え込まず、支援を受けながら適切な対応を模索することが求められます。
カウンセリングを定期的に利用することで、子ども自身が「話せる場所」「理解される経験」を積み重ねていけるようになります。心理的な安全基地を確保することが、長期的な自立支援にもつながります。
まとめ
不登校は、誰にでも起こりうる身近な問題です。「甘え」や「怠けている」と勘違いされがちですが、実際には人間関係や学業、家庭環境など、さまざまな要因が複雑に絡んでいます。表面的な行動だけを見て判断するのではなく、子どもが抱えている不安や悩みに寄り添うことが大切です。保護者の役割は「安心できる場所」と「信頼できる人」を見つけてあげることです。学校以外の選択肢も視野に入れ、再び社会とつながれるように長い目で支えてあげると良いでしょう。地域によってはフリースクールと連携したサポートを用意していることもあるため、気になる方は自治体の相談窓口に問い合わせてみると良いでしょう。本記事が参考になれば幸いです。